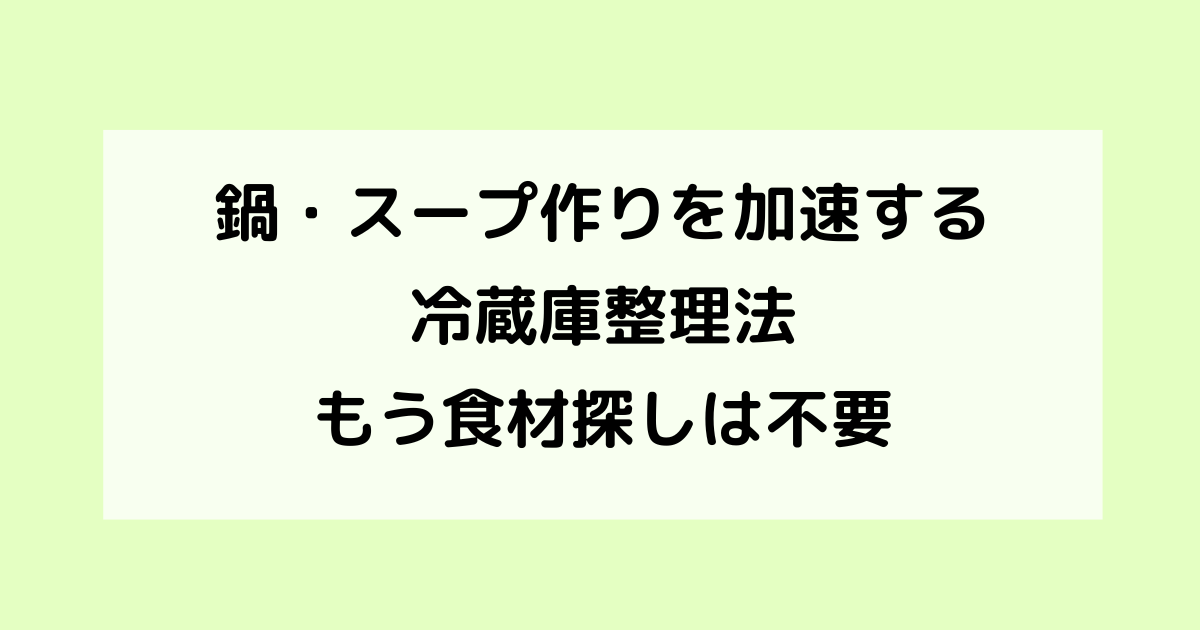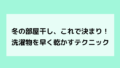寒い季節になると、あたたかい鍋やスープを作る機会が増えますよね。
でも、いざ作ろうと思ったときに「野菜がどこにあるかわからない」「買っておいた豆腐が見当たらない」と、冷蔵庫の中で食材探しに時間がかかってしまうことはありませんか?
そんな悩みを解消するのが、冷蔵庫の整理整頓です。
少しの工夫で、鍋やスープの準備がぐんと楽になり、料理の時間を短縮できます。
今回は、100均アイテムを使った実践的な整理術や、鮮度を保つ収納のコツをご紹介します。
冷蔵庫の整理術|ダイソーやセリアの活用法

ダイソーの収納アイテムで整理整頓
ダイソーには、冷蔵庫用の仕切りボックスや引き出しタイプのトレーが豊富に揃っています。
たとえば「仕切り付きトレー」を使えば、野菜・肉・魚などのジャンルごとに分けて収納でき、取り出しもスムーズになります。
また、調味料を立てて入れられる「冷蔵庫用ラック」を使うと、奥に入った瓶類も一目で見えるようになり、取り出しやすくなります。
セリアの便利なアイテムを駆使した保存法
セリアの「クリアボックス」や「密閉容器」は、見た目もすっきりして中身が確認しやすいのが魅力。
スープ用の野菜やカットした豆腐を入れておけば、下ごしらえの手間が減り、使いたいときにすぐ取り出せます。
さらに、ラベルシールを使って「にんじん」「白菜」などと名前を書いておくと、家族も迷わず取り出せるようになります。
100均で揃える!野菜室整理のコツ
野菜室はついごちゃつきやすい場所。
ダイソーやセリアの「深型バスケット」や「仕切りケース」を活用し、根菜類・葉物類・きのこ類などのグループごとに分けましょう。
分類しておくことで、使い忘れも防げ、食材ロスの軽減にもつながります。
野菜室をきちんと整理する方法|食材の鮮度を保つ

使いかけの野菜の収納方法
半分使ったキャベツや玉ねぎは、ラップだけでは乾燥しやすいため、密閉袋や保存容器に入れて保管します。
野菜の切り口にはキッチンペーパーを軽く当ててから袋に入れると、余分な水分を吸い取り鮮度を保ちやすくなります。
また、冷気の当たりすぎを防ぐため、保存袋を立てて収納するのもおすすめです。
さらに、使いかけ野菜を一カ所にまとめる「使いかけボックス」を作ることで、どの野菜が残っているのかひと目で把握できます。
鍋やスープを作る際も、迷わず残り食材を使えて時短につながります。
収納ボックスの上手な使い方
ボックスを「浅型」と「深型」で使い分けましょう。
浅型には葉物やきのこ類、深型には根菜類を入れると、重なっても取り出しやすくなります。
さらに、ボックスにすのこ状の仕切りを入れておくと、底がぬれにくく野菜の鮮度を保ちやすくなります。
引き出し式のものを選べば、掃除もしやすく、いつも清潔に保てます。
また、種類ごとにラベルを貼っておくと、家族も食材を探しやすく、誰でも元の位置に戻せる仕組みが整います。
紙袋を活用した野菜収納のアイデア
紙袋は湿気を適度に吸収してくれるので、じゃがいもや玉ねぎの保存にもぴったりです。
見た目もナチュラルで、冷蔵庫内が優しい雰囲気になります。
さらに、紙袋の中に新聞紙を敷くと、湿気をよりコントロールしやすくなり、根菜類の保存期間も長持ちします。
紙袋にマスキングテープでラベルを貼っておくと、管理がさらに楽になります。
調味料や豆腐、納豆の適切な保管方法

冷蔵庫のドアポケットの整理
ドアポケットは調味料であふれがちです。
使用頻度の高いものを手前に、賞味期限の長いものを奥に配置するのがコツです。
100均の「小分けラック」や「ドアポケット用仕切り」で倒れ防止すると、見た目もスッキリします。
さらに、ボトルやチューブを種類ごとに立てて収納できるトレーを使えば、取り出しやすく清潔に保てます。
調味料キャップ周りの汚れ防止には、ペーパーナプキンを下に敷くと簡単に掃除ができて衛生的です。
また、月に一度は中身をすべて取り出して拭き掃除をすると、カビやぬめりを防げます。
上段・下段のスペースを効率的に使うコツ
冷蔵庫の上段は温度がやや高めなので、調味料や飲み物を置くのに向いています。
ジャムや味噌など、開封後も冷蔵保存が必要な食品もここにまとめておくと便利です。
下段は温度が低いため、肉や魚、豆腐など傷みやすい食材を入れるのが理想です。
豆腐や納豆はパックごと保存容器にまとめて入れておくと、液漏れ防止にもなります。
分類ルールを決めておくと、家族の誰が使っても迷わず、出し入れもスムーズ。
さらに、定期的に賞味期限を確認する「チェックデー」を設けると、食材ロスを減らせます。
冷凍庫の工夫|長持ちさせる保存方法
冷凍庫は「立てて収納」が鉄則。
100均の「ファイルスタンド」や「ジッパーバッグスタンド」を使えば、冷凍した食材を本のように並べて収納できます。
スープの具材を小分けにして冷凍しておくと、忙しい日でも手早く鍋が作れます。
また、食材を種類ごとに袋の色やラベルを変えておくと、どれが野菜でどれが肉なのか一目でわかります。
さらに、冷凍庫の奥には「ストックコーナー」を設けておくと、買いすぎ防止や在庫管理にも役立ちます。
定期的に冷凍庫の霜取りや整理を行えば、電気効率も良くなり、節電効果も期待できます。
自宅でできる、食品ロスを減らすための賢い工夫

食材の賞味期限を上手に管理するポイント
毎日の食事作りで「気づいたら賞味期限が切れていた…」という経験はありませんか?
そんなときにおすすめなのが、冷蔵庫の中を“見える化”する工夫です。
たとえば、冷蔵庫の扉や棚の内側に「賞味期限メモ」を貼っておくと、ひと目で食材の状態が確認できます。
さらに、調味料や開封したパック食品には、マスキングテープを使って「開封日」を書いて貼るのが便利です。
見た目もスッキリして、どれを先に使うべきかがすぐ分かります。
また、冷蔵庫の中で古いものを奥に追いやらないよう、「手前に古いもの、奥に新しいもの」を並べる「先入れ先出し」ルールを意識するのも大切です。
こうした小さな工夫で、無駄をぐっと減らせます。
無駄を出さない買い物リストの作り方
つい買いすぎてしまう原因の多くは、「家に何があるか分からないまま買い物に行くこと」。
そんなときは、買い物前に冷蔵庫の中をスマホで写真に撮るだけでOKです。
写真を見ながら買い物をすれば、「同じ野菜をまた買っちゃった」という失敗が減ります。
さらに、買い物リストアプリを活用すると、もっと効率的です。
アプリに「よく使う食材」や「今週の献立予定」を登録しておけば、必要な分だけを無駄なく購入できます。
余った調味料や食材の上手な使い切りアイデア
冷蔵庫の奥に、少しだけ残った調味料や野菜の切れ端が眠っていませんか?
それらを上手に使い切ることも、食品ロスを減らす大切なポイントです。
たとえば、少量の味噌やポン酢はスープや炒め物の隠し味にぴったり。味に深みを出してくれます。
また、野菜の皮や茎、切れ端は、コンソメやだしと一緒に煮込めば「野菜の旨みが詰まったスープ」に大変身。
さらに、使い切れない調味料は小さな製氷皿に入れて冷凍保存しておくのもおすすめです。
必要なときに1個ずつ取り出せて、とても便利です。
まとめ
冷蔵庫を整えるだけで、鍋やスープ作りがぐんとスムーズになります。
100均アイテムを活用しながら、自分の使いやすい収納ルールを見つけてみましょう。
整理された冷蔵庫は、料理の時間を短くするだけでなく、気持ちにもゆとりを生んでくれます。